――――「夜乃月学園」
その学園への入学は、間違いなく僕の人生にとって大きな転機だったと思う。
それは入学が決まったときからなんとなく心の奥底で理解していた。
客観的に見ても、そう思えるくらいには衝撃的な波乱の幕開けだったはずだ。
ただ、そうなったのが偶然ではなく必然であったのだと知ることになるのは、僕が入学してから相当後の事だった。
夜乃月市。
元は利用価値の高い広大な土地がそのまま広大な農地や広場として点在しているような、のどかな場所だった。
寂れているわけではなく、人口そこそこ、商業発展もそこそこといった感じで、住みやすさとしてはなかなかに良い。
実際生まれ育った僕も、そんな夜乃月という場所を好ましく思っていた。
しかし、今は大きく様変わりしている。
国の政策により、大規模な開発が行われたんだ。
元より発展するポテンシャルは持っていたのだから、お金が投入されれば開発は一気に進む。
というわけで、あっという間に『夜乃月市』と『市』として成り立つほどに発展を遂げたのだった。
そう聞くと、単に開発の余地のあった場所が国の政策によって開発された、という話だと思うだろう。
だが、実際のところ国の財政は夜乃月のような場所を発展させるほどの余裕はない。
一自治体の発展に国が介入するなんていうのは特別な理由なしには起こりえないのだ。
ではなぜ、夜乃月市では起こりえたか?
それは、国の政策としながらも国はお金を出していないからだ。
お金を出した人物は他にいる。
そして、その人物は「国の政策」という体で夜乃月を開発することに関し、国から「YES」という回答を引き出した人物である。
夜乃月雫。
夜乃月学園を設立した理事長であり、莫大な資産と権力を有しているとか。
要するに、その資産力と権力でもって、夜乃月の開発を強行し、表向きは国が主導で行ったのだということにさせたんだ。
それだけの力を持っているということなんだろう。
素性は公開されておらず、とにかくなんかすごいという、都市伝説みたいな存在になっている。
よく言えば自由、悪くいえば横暴な人なのだろう。
ただ、その理事長の行動にはある程度目的のようなものが見てとれる。
夜乃月学園は国により国家特別教育機関に指定されている。
まあ、その指定および国家特別教育機関という枠組み自体、理事長が新たに作り出したものだけど。
潤沢な資金でもって整えられた高度な設備を数多く有する、世界的に見ても希に見る教育機関として夜乃月学園は設立されたんだ。
元々その場所には「夜乃月高等学校」という高校が存在していたけど、今は見る影もない。
そして、その夜乃月学園を中心にあらゆる商業施設や生活に必要な機関が建設されている。
つまり、教育機関である「夜乃月学園」およびそこに通う生徒の生活環境を整えることに注力しているということだ。
それだけ教育分野に興味関心があるということなのだろうか?
恐らく関心はあるのだろうけど、やり方が強引であることや、学園自体が多くの謎に包まれていることなども考慮すると、別の意図があるようにも思える。
そんな夜乃月学園への入学が決定した。
そこに僕の意志は存在しない。
夜乃月学園の入学選考基準は謎であり、強いて言えば理事長の独断。
選考に必要なパーソナルな情報は、理事長が独自に調べているらしいが、個人情報という概念はどこへやら。
僕の何が例の理事長にその判断をさせたのかは不明だけど、幸か不幸か僕の高校生活は夜乃月学園で始まることになった。
――――夜乃月学園が設立されて三度目の入学式当日。
これで、夜乃月学園も三学年が埋まり、高校としてのある意味フル稼動していると言えるだろう。
少なくともこれまで学園の運営が続いているという点では、少し安心できる。
もっとも、金銭面で破綻することはほぼないだろうけど。
入学式は形式的だった。
強いて変わったところといえば、理事長の祝辞がスピーカー越しに行われ、姿を見せなかったことくらいだろうか。
学園内においても、素性は明かさないスタンスなのだろうか?
声を聞く限り、どことなくお気楽な印象を受けたので、単に出てくるのが面倒であった可能性も捨てきれない。
ともあれ、入学式は滞りなく終わり、僕は張り出されたクラス分けの表に従い二階へと向かった。
1年A組。
そうプレートが掲げられた教室に入り、ホワイトボードに貼られた座席表を見る。
最前列窓際。
学年はともかく、何かと前の方だなと思ったけど、自分の名字が『あ行』であることを考えると、割りと納得出来た。
とりあえず席に着き、これからしばらくは過ごすであろう定位置からの眺めを確認する。
窓から見える景色は、かつての夜乃月とさほど変わりはない。
開発されたと言っても、学園と周辺の主要な建物以外は当時の姿を維持している。
多少道路なんかも新しく舗装されたりはしたけど、利便性が向上したくらいで、古いものを壊してまで開発された部分は多くない。
住民の理解を得るため、というのもあるだろうけど、そもそも理事長は夜乃月市そのものを急速に発展させるつもりは無いように思える。
必要な建物を建て、それを維持するために必要なことをする。
それ以外のことに興味はないのだろう。
元の住民も、受けられる恩恵の方が大きいだろうし、その辺りは上手く関係性を構築し、持ちつ持たれつという感じだ。
学園生に至っては、その恩恵を最大限に受けられるので、ここに入学できたのはラッキーなのかも知れない。
「まさか合格出来るとはなぁ。ねぇ、君?」
ぼーっと夜乃月の発展について考えていると、突然横から声をかけられた。
「……ん? えっと、君は……?」
恐らくクラスメイトなのだろう。
交友関係の構築に関しては奥手な方なので、こうやって初めて会うクラスメイトに声をかけることの出来る人はどことなく無条件で尊敬してしまう。
僕自身が、そういう人に声をかけられやすいという体質なのもあるのだろうけど。
「ああっと! いきなりすまないね。僕の名前は棚江修一、今日から君のクラスメイトになるものだよ! この学園って入学難度恐ろしく高いから、僕なんかじゃ無理かもって思ってたけど、結果的に合格してしまったからびっくりだよ! それはさておき……せっかく同じクラスになったんだ。今日からよろしくね!」
なんとも軽快に話しかけてきた棚江と名乗る人物に少々戸惑いつつ、僕は返答する。
「そうだね、よろしく棚江君。僕は……」
相手が名乗ったのであれば、こちらも名乗る。
これからともに学園生活を送る上で互いに名前を知ることは必要だ。
だから僕も自己紹介をしようとしたのだが、それは途中で遮られてしまった。
「おおっと! 知っているよ、ほたるん!」
「ほたるん……?」
馴れ馴れしいとかそういうのは気にしない性格だけど、聞き慣れない呼び方に戸惑う。
「世界的科学者、蒼祈万象氏と美人ジャーナリストの蒼祈御代氏のご子息。蒼祈ほたる君……だよね?」
妙なプレッシャーと期待が感じられるけど、彼の言っていることは事実だ。
「うん、そうだけど……ほたるん?」
有名人である父さんや母さんはともかく、無名な僕をなぜ知っているのか?
なぜそのようなあだ名で呼ぶほど親しみを持っているのか?
疑問が湧き出るように生まれる。
「その呼び方……」
「ダメかな? ネット上ではみんなそのニックネームで呼んでるんだけど?」
などと更に疑問が深まるようなことを言う。
「ネット上で……って初耳なんだけど?」
「一般には公開されないはずの情報だもんね」
彼は知っている。
知った上で、僕の存在を特定している。
なおさら不思議だ。
「僕の存在は……」
「蒼祈万象と蒼祈御代の間に子供はいない。本当は存在していて、それが息子である事実も、名前も、年齢も、その姿も秘匿されている……だよね?」
「君は物知りなんだね。いや、物知りとかいう域を超えているけど」
「君にとってはそうかもね。やっぱり君は、僕が想像したとおりの人だね」
「どういう意味?」
「べっつに~。ただ僕は嬉しいんだ、君に会えたことがね。さて、そろそろ君の疑問にも答えないとね」
「どうして、僕の存在を知っているのか」
「そう。どういう理由かは分からないけど、蒼祈万象氏はフィルタープログラムを構築し、ネット上に君の情報が流出しない、そしてアクセスできない仕組みを用意した。そのシステムは正常に稼動し、今日に至るまで君の存在は極一部の人しか知り得ないものとなっている……一般にはね?」
棚江君はウインクして話を続ける。
「実は蒼祈万象氏の開発したフィルタープログラムは、一度ハッキングされているんだ」
「えっ!?」
「ふっふふ、驚いた?」
なんとも楽しそうに棚江君は言った。
もちろん驚いた。
自慢じゃないけど、父さんのプログラミング技術は一般的なレベルを遙かに凌駕している。
優秀なハッカーでもそれを解析してデータを入手するのは困難だろう。
絶対に不可能とは言わないけど。
僕は今まで家庭学習で教育を受けてきたし、近所づきあいもあまりない。
あっても写真を撮られたことなど一度もないし、家庭内でも写真を撮る習慣は皆無だ。
もしかしたら、僕が知らないだけで僕が写真を撮られていた可能性はある。
だけど、その画像がネットのフィルターをすり抜け、もしくはハッカーがフィルターを超えて画像保有者から入手するなんていうのは、そうそう起こりえないことだ。
だからこそ、機能する。
いや、棚江君の話が事実なら、機能していた、か。
「ということは、僕の姿は一部の人には知られているということ?」
「それについては心配要らないよ。フィルタープログラムをハッキングしたハッカーはその辺を気遣うタイプだからね。むしろプログラムの脆弱な部分を補強して、より強固なプロテクトに改変しているくらいだから。目的はあくまで技術的挑戦だったみたい。ネットのディープな所で一時的に流出したけど、データ保有者から強制的にデータは回収消去されているんだ」
「でも、人間の脳内にある情報までは削除できない……」
「さすが、ほたるん! ハッカーの間では珍しい出来事だから、彼らは君に興味と関心をもって『ほたるん』と呼んでいるんだ」
その後も棚江君は色々教えてくれた。
ハッキングの成功に気づいたハッカーはごく僅かで、そのハッカー達も情報を広める気はないとのこと。
それは、情報が父さんがらみだということが大きいらしい。
並の科学者ならともかく、蒼祈万象という科学者は敵に回せばまずい。
それほど有能で底の知れない存在だと認識されているようだ。
「――それに、ほたるんの姿が映った画像データを見たのは、そのハッキングを成功させたハッカーと僕だけなんだ、安心して」
ということらしいが。
ハッキングしたら当人はともかく、棚江君はどうして見ることが出来たのだろう?
「あ、僕がどうしてほたるんの姿を知っているのか不思議に思っているね?」
「まあ、不思議というか、怪しいというか……。棚江君もハッカーだったりするの?」
その質問に彼は首を横に振る。
「僕は運良くそのハッカーと連絡が取れる間柄でね。特徴だけ少し教えてもらったんだ。さっき画像データを見たって言っちゃったけど、直接は見ていないんだ」
そこはそのハッカーなりの配慮なのだろう。
情報の漏洩を徹底的に防ぐのであれば、特徴すらも伝えるべきではないのだろうけど、棚江君が情報を得られたのはそれこそ、そのハッカーとの関係性ゆえなのだろう。
「それにしてもよくその特徴だけで僕が分かったね。詳細な特徴を教えてもらったのかな?」
「ううん。本当に端的な情報だけだよ」
「だったらそれを僕に教えてもらえたりしないかな?」
端的であるのであれば、短い時間で教えてもらえると考えたのだけど、棚江君の返答は僕の望むものではなかった。
「んふふ~、内緒♪」
「内緒ですか?」
「内緒ですっ♪」
棚江君はまた楽しそうに答えた。
その返答に僕は嫌悪感を覚えることはなかった。
それどころか好感を抱きさえした。
この短時間で、初対面で、これだけ気軽に僕と会話が出来ることに感動する。
棚江君という存在を、軽快にプレゼンされたような気分だ。
少なくとも僕は彼のことを好ましく思っている。
「それにしても父さんのプログラムを突破するなんて、そのハッカーはすごいね。そのハッカーと連絡がとれる君もすごいというか怪しいけどね」
「あっはは! 僕のことはともかく、そのハッカーは本当にすごいよ。ネットでは『WinterFox』って呼ばれてて……」
棚江君は凄腕ハッカーの話を意気揚々と始めたけど、すぐに担任らしき先生が教室に入ってきたので会話は中断された。
――――およそ二十分後。
「――明日から通常授業も始まるからな、テキスト忘れるんじゃないぞ! それでは今日は解散!」
担任の茂野先生は、必要な情報を話すと教室から去って行った。
年齢は分からないけど、若い部類に入る人だろう。
更に若い僕が思うのは変なのかもしれないけど。
活気がありさっぱりした印象を受けた。
本日の学園行事は終了。
この後は特に予定もないので、棚江君に先ほどの話の続きでも聞こうかな。
彼の都合が良ければだけど。
そう思って棚江君の姿を探していると……妙な音が聞こえてきた。
「ザ、ザザ……ザザーー。……ガチャ……! ガガッ……もうっ! なんで呼び出し音壊れてるのよ!? ぴ……ぴんぽんぱんぽ~ん。……え~っと、1年A組の蒼祈ほたる君……というか、ほたるん! 至急理事長室まで来てね~♪」
……なんと個性的な呼び出しアナウンスだろうか。
というか僕? 理事長が入学初日に何の用!?
新鮮な疑問がどんどん湧いてくる。
「理事長から呼び出されるとは大変だね、ほたるん」
「そ、そうだね。それにしても、またほたるんって……」
「まあ、ほたるんは有名だからね」
「僅かなハッカーしか知らないんじゃないの? 有名だと困るんだけど」
「そうだったね、ごめんごめん。ただ夜乃月学園理事長の情報収集能力は有名だからね。知られてしまっても不思議ではないね」
なぜか棚江君は自慢げだ。
「とにかく行ってくるよ……」
「うん、またゆっくり話そう! またね、ほたるん♪」
今日一日で何度ほたるんと呼ばれただろうか?
このまま学園内でこの呼び方が浸透しなければ良いけど。
僕は複雑な気持ちを抱えつつ、理事長室へと向かうのだった。
夜乃月学園理事長。
謎多きその人物に目をつけられたことに心はざわつく。
単なる事務的な用事である可能性もゼロでは無いだろうけど、その可能性は低いだろう。
夜乃月学園に入学すること自体僕の中では予定調和とはほど遠い出来事ではあるのだけど、更なる予定外の訪れを感じつつある。
だけど、僕の足は着実にその予定外へと進んでいて、自己の意志と予期せぬ力の強制力との調和に身を任せながら、夜乃月学園の空気に慣れていこうと決意するのだった。
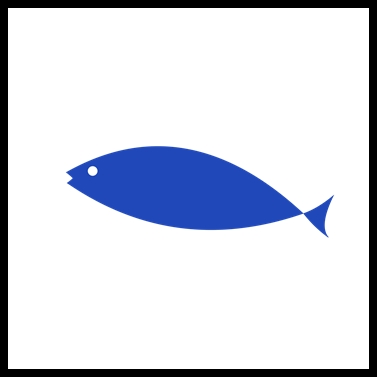 鯛焼ぷろじぇくと。Official Website
鯛焼ぷろじぇくと。Official Website 